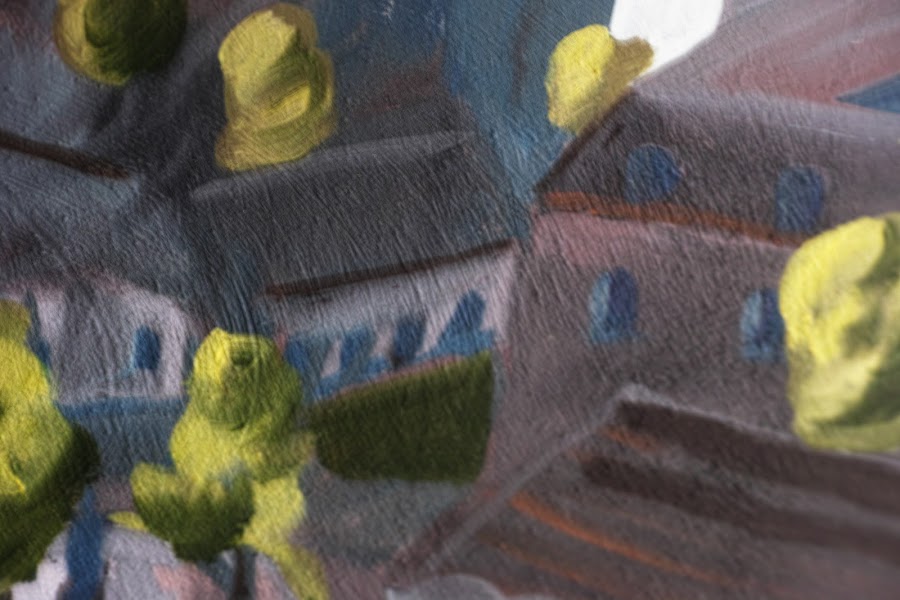「さがるまーた」は新創刊の 絵本雑誌。
11月末発売から半月、とても話題になっているようだ。
同誌に棍棒で話題の東 樫さんの作で、わたしが絵を担当させていただいた読み切り短編絵本「棍棒バアアアン」が掲載されている。この雑誌に参加できて光栄。
テキストは、ドッカアアンとかバアアアンとか、擬音ばかりだったので、とりあえず東さんが棍棒を振り回しておられる奈良の地へ取材に向かった。
わたしは東さんの東「千茅」名義でのご著書「人類堆肥化計画」を楽しく拝読しており、ますます興味が湧いた。今、東さんを夢中にさせている棍棒とは何か。
電車とバスを乗り継いでまず大宇陀のグランドに向かう。東さんが仲間と共に考案した「棍棒」を使った独自の競技、その練習場である。
この競技は棍棒で棍棒を打撃し叩き飛ばす。それをまた棍棒で打ち返す。砲丸投げ、野球、ゴルフ、アイスホッケーなどの要素が取り込まれたルールはまだ発展途上らしい。
山で伐ったいろんな樹を加工した棍棒が並んでいる。加工といっても、樹が「材」になるだいぶ手前の加工度なので、何やらそこにはまだ森の霊力のようなものが残存した呪具のような畏れ多さを感じる。「これが棍棒か」。参加者のみなさんはすでに棍棒の魅力に囚われているようだ。おのおのの手に馴染む棍棒を選び、それぞれ独自の殴打フォームを完成させている。わたしも何度か打たせてもらったが、打撃の瞬間、狂気のような振り切れ感があって、自分、怖!と思った。
場所を移動して「人類堆肥化計画」に書かれていた畑も見学させてもらう。小川の流れる山林と棚田。最高の場所だった。外からはこんなところがあるなんて全然わからない。東さんが棍棒に夢中になりすぎてちょっと畑が荒れていたのがなんか良かった。
そしてそこには棍棒競技の特訓場があった。そこまでやるのか。グランドで見た東さんのぐるんと回転して棍棒を振り下ろす美しい打撃フォームはここで完成したのだろうか。わたしもいつか自分の棍棒の振り回し方と出会わなければいけないような気がしてきた。
*
さて、肝心の絵はどんな風になったか。兎に角、描き終わったときの気分が痛快だった!とだけ書いておく。わたしも棍棒とまではいかないが、いろいろな枝を集めて室内に飾っている。(最近その集める枝が小枝だったのがどんどん太くなってきているのが気になるがw)植物の組織のうねりや分岐、ベージュや茶色の奥深さ、さまざまなテクスチャが楽しい。
わたしは「植物」とは、その形状や生態の不思議さから、外界へ向けられた何らかのアンテナではあるまいかと思っているので、東さんのテキストの中で巨木がドカアアンと伐採され、棍棒がバアアアンとつくり出され、人から人の手へと渡ってゆき、競技になって、そして、お終いには「宇宙誕生」というところまで持っていくというテキストの流れは案外強引ではなかったと感じている。
「さがるまーた」は強力な絵本の短編で埋めつくされた雑誌だ。ポスターや別冊絵本までついている。わたしの個人的恩人編集者たちの対談もある。
講談社の編集者がたったひとりで作り上げた。わたしがあまり気にするべきことではないけど、将来この本にはプレミアムがつくのではないかと思っている。アートの名雑誌「ミノトール」や「漢聲」のようになってしまうのかも?
ぜひ雑誌「さがるまーた」創刊号をゲットしてご覧いただけたら嬉しいです。
ナカバアアアン拝。